「スマホ時代の哲学」を読み、学びをアウトプットした。読めば読むほど、紹介するのが難しい本だった。
表面をなぞるだけなら至極簡単で、「要はスマホ(SNS)の使い過ぎに気をつけて、代わりに趣味に没頭しよう!」という話だ。
“要は”、ね。
要した結果ではなく、要せなかった文脈——その隙間に本質はある。別にこの本に限ったことではないが。
この本は、SNS時代に生きる私たちの在り方をネタバレしてくる。
エナジードリンクを買って気合を入れるアッパーな朝と、チルい音楽やネトフリに浸るダウナーな夜を繰り返す。それっぽいことをそれっぽくこなす日々。それって商品やコンテンツじゃなくて、『それっぽい私がなんか良いよね』が欲しいだけでしょ。なんて、痛いところを突いてくる。
スマートフォンはどこに置いても世界を繋ぐ。悪い意味で、(意識が)どこへでもドア。我々は常に孤立を失い、やがて孤独を忘れる。
ひとりじゃ何も考えられなくなっている。いや、考えるための独り時間がないのだ。
誰にとっても分かりやすく、誰にでも扱えるよう設計された“親切さ”。その便利さに慣れてしまうと、世の中には「誰にも分からないもの」や「何のためにあるか分からないもの」が溢れているということを、つい見落としてしまう。床に落ちた毛髪をただのゴミとして扱うように、一度“別物”と判断したものを、拾い直すことはもうない。
誰でも使えるように、と考えられたユニバーサルなデザインは、もともと備わっていた機能や秩序までも廃れさせてしまってはいないだろうか。効率的に使うことが、いつしか遊びにも効率を求めるようになっていないだろうか。不効率で無駄だからこそ人は遊び、余白や余剰に宿る遊び心から創造は始まる。
合意形成よりも、コミュニケーションそのものが目的になったコミュニケーションによって思考が記号化されていく。ゆるい規則(ルール)の中で、ゆるい意味をもって行われる。伝え手の手間を省き、受け手の解釈に負荷を寄せた結果、みんなが読解力を求めて彷徨う。
私調べでは、読解力は複雑で複合的な能力であるため、教科書通りには扱えない。それ即ち、人間力とも言える。
「生涯学習」が謳われて久しい。今では「人生100年時代」「リスキリング」と名前を変えて、社会構造の歪みを包むオブラートが変わっただけで、中身の飲み込みにくさは変わらない。
薬をうまく飲めない子どもに「あんたの飲み方が悪いのよ」と説教するような、そんな気まずさがいつも伴う。読解力の低下やメンタルヘルスの悪化は自己責任で片付けられる話ではない。そんなに簡単なら、我々はリハビリテーションなんてやっていない。
社会を土壌とするならば、情報は水源だろうか。良い土と良い水があれば良い実りが得られそうだ。……って、気づけばまた生産性を計算している。
実りよりも、育むその過程にこそ哲学は宿る。
何かを育むことで、不確実性と向き合うことができる。自分の中にいる他者を知ることができる。過剰になった自己関心から、自己対話へとシフトをチェンジする。
自己対話をするためには、趣味が必要だ。
趣味活動。元々ろくでもない人間の暇つぶし。没頭できるか、それともただの気晴らしに終わるか。
私はダンスとイラストを始めた。……始めたと言っても、気が向いた時にぽつりぽつりとやる程度だ。ダンスは季節に一回ほどだが、運動不足と脳の刺激不足を解消するために。イラストは子どもたちのリクエストに応えて推しキャラを描く。
ずっと苦手だと思っていたし、自分には向いていないと決めつけていたかもしれない。上手い人と比べ、思い通りにいかない苦しさから逃げるための口実だったのかもしれない。
大人になれば、誰と争う必要もない。お金をもらうでもない。
些細な暇つぶし。
でも、それが楽しくて仕方ない。新しい自分に出会える。“生みの苦しみ”の割に褒めてもらえたり、喜ばれたりする。良い意味でコスパが合わない。没頭に他人の評価基準は当てはまらない。
やってみて気づくことがある。挑戦の先に没頭があり、没頭の先に自己対話がある。衝動に背中を突き飛ばされて始めた配信ラジオ。それをまとめたリール動画に対して著者からリアクションをもらえるなんて、人生は分からないものだ。どうやら届く人には本当に届くらしい。
モヤモヤをモヤモヤしたまま呑み込む。分からないものを分からないまま抱える。
私は自分のことをグリットが高い人間だと自負している。だが、「ネガティブケイパビリティが高い」という説明の方が、性に合っている気がする。グリットは高められなくても、ネガティブケイパビリティなら高められる気がする。
運動制御について研究しているのも、分からないものを分かりたいから。学ぶほどに分からないことが増えていく。
作家として言語化したいのも、モヤモヤと対峙していたいから。外側を向いても内側を向いても、どうせモヤモヤは止まらない。
死ぬまで臨床家でありたいと思えるのも、人間への興味が尽きないからだ。わけのわからん生命体め。くたばるその時まで対峙してやるよ。
この本は「読めば何かが分かる本」ではない。でも、読めば一皮剥けた気持ちになる。薄皮一枚分だけ自分に近づく。人生の本棚に置き、何度でも読みたくなる一冊だ。
何度も皮を剥いたところで中身はないかもしれないが。

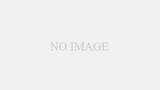

コメント