本を貸し借りする。母と、義母と、友と。時々、患者と。
この本も母から借りて長らく読めていなかったが、返す機会が限られていると読む優先度が高まる。
実家に帰省すると手持ち無沙汰になるが、読書はそれを解決するのにピッタリだ。
電車で読む時は物語を数行ずつ読み進めていくが、連休となると数冊読めてしまう。
久しぶりに寝泊まりする部屋数の多い家で、久しぶりに会える従兄弟たちと遊び、子供たちはいつもの数倍騒がしい。
そんな中でも久しぶりに本を一気読みできることに「まだまだ読めるじゃん」と安心と自信を取り戻す。
『そして、バトンは渡された』
親の愛情は無限でも、それを伝えられる時間は無期限ではない。
私に残された役割と時間を確かめる。
これは家族の物語ではない。人から人へ、想いをつなぐ物語。
物語に登場する大人は大体、保護者か教師である。自然と読者の目線もそれに近くなる。
少女の人生を共に見守る。
血の繋がりがなくても、養う経済力がなくても、親を名乗れるほどの年齢が足りなくても、共に過ごした時間はその関係性を否定しない。
だから少女の生活に事件は起きない。悪人も登場しない。
学校から帰宅した我が子からその日の様子を聞くように物語に耳を傾ける。
「学校は楽しい?」
「勉強は大変じゃない?」
「友達と上手くやっていけている?」
ページをめくり、少女の生活に寄り添い、人生を辿る。
いつしか彼女は愛情を受け取る側から愛情を捧げる側へ。
与えるほど、与えられてきた愛情の豊かさに気づくだろう。
彼女を見守ってきた読者も、たくさんの親のひとりとしてその門出を見守る。
読了後に残るあたたかさは、未来に向かって繋がれたバトンを握るぬくもりだ。

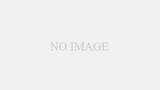
コメント