最寄り駅の改札を抜けて階段を降りると、パステルグリーンのスクールバスがロータリーで折り返していた。見るだけで懐かしさが込み上げる。蒸し暑さはまだ残っていたが、それでも迷わずバス停を通り過ぎた。
記憶の中の景色と街並みをすり合わせたくて、歩いて大学に向かう。あの頃に産まれた子が成人になるほどの時間が過ぎようとしている。今も何も変わらずに残っているものと、今ではもうすっかり変わってしまったもの。目に見える変化は親切で分かりやすく、街そのものが時計のような役割を果たす。私がようやく1周したかと思う頃に後輩達は目まぐるしく60周している。恩師達は今も変わらぬ見た目と優しさのまま、まるで歳を取らない生き物のようにゆっくりと、だが着実に大きく一歩進んでいる。秒針、長針、短針にそれぞれの生き様がある。
街並みに限らず、今を生きる人や、この仕事に対する情熱も同じように変化していく。目に見えるだけマシかもしれない。知らぬ間に失ってしまったものは気づくことすらできない。無くしたくない大切なものを確かめるために何度でも足を運ぶ。もう戻れない日々を背にしながら、せめて明日へ向かえるように。
先日、母校で行われた卒業生による学術交流会は、今年で3回目の開催となる。私は3年連続3回目の発表をした。一昨年は人生とキャリアについて、昨年は専門性と自論について、そして今年は普段の臨床のありのままを症例検討という形で伝えた。
発表セクションの前に、学長による特別基調講演があった。テーマは理学療法士の「未来の選択」。私達の仕事は医療技術職の中でも治療職であることを強調されていた。患者を良くできるやりがいも、良くできない困難も、その場にいる皆が知っている。日々の経験と学びは目の前の患者に還元され、また患者に向き合うことで自らの仕事や生活の糧としていく。
『お前の患者は良くなっていない』
学長の苦く暗い時代に共感するには、同等の熱量が必要だ。今の若手理学療法士にこの話がどこまで刺さるのだろうかと気になった。私たちは自分でコントロールできる範疇でしか物事をコントロールすることはできない。これは当たり前のことだ。他人の思考や言動ではなく、自分自身の思考や言動を変える。明日の天気は変えられなくても、今日のうちに傘を用意することはできる。講演のキーワードでもあった「メタ認知」を高めることによって人間的な成長を図ることは、一つの人生の解法であり、そして永遠の課題でもある。
もう一度言う。永遠の課題なのだ。解法とは単に課題との向き合い方に他ならない。理学療法士が先輩たちから学ぶべきことは明快な解答ではない。ゴッドハンドになれる方法でも、インフルエンサーになれる方法でも、効率的なビジネスモデルでもない。「誰にでもわかる」まで引き算された苦く暗い足跡から学ぶことがある。
懇切丁寧な世の中だと思う。「分かりやすい〇〇」、「誰にでもわかる〇〇」、溢れる動画コンテンツも、誰もが暮らせるバリアフリーな居住空間も、実習中や新人時代の課題も。恩恵を享受しておきながら言うことではないが、懇切丁寧過ぎて頭が痛くなる。イージーモードの何が楽しいのだろうか。武器を手放しては冒険には出られない。挙句、失ってしまったその能力でも戦える異世界へ、転生でもするつもりだろうか。ブルーオーシャンを目指すのはいいが、ゼロに何を掛け算しようが、それはゼロにしかならない。
これは若い世代に限った話ではなく、これからを生きる人にとっての共通問題でもある。世の中や社会といった自分自身を取り巻く環境において、自分の力ではどうしようもない不確実性が強く高まっているのも事実だと思う。知らないことには不安は拭えず、生き残るための戦略を見いだせない。しかし、情報の民主化が負に作用し、自分の人生の豊かさに全く影響しないものや、理学療法士として、その時に考えなくてもいい事まで知ってしまった結果、患者と向き合う集中力が削られている気がしてならない。自分でコントロールできていたはずのことすら、コントロールできなくなっている。知的労働者として致命的な方向に全体が向かっている気がする。
頑張れよ、という一言でさえ、額面通りに受け取っていいものだろうか。どう何を頑張ればいいのかは、今だによく分からない。だからずっと考えている。
特別な理学療法士になんてなる必要はない、と言いたいところだが、普通の理学療法士でいること自体が難しくなっているのかもしれない(そもそもその”普通”が最初から無いのかもしれないし、お前の普通は普通じゃないとか、古くなったお前の価値観だと言われたらそれまで)。産まれた順列を気にする必要はないが、あえて”先輩”として助言するならば、大学の先生のように臨床と研究と教育をバランスよく取り組んでいる人をモデルにするのもいいが、それよりも日々の仕事で自身が患者と向き合っている時間を大切にすればいいということを伝えたい。治療職で技術職である以上、臨床に取り組んでいる時間は何にも代え難い財産となる。それをもっと強く自覚して良い。
なのに職域や給与といったキャリアデザインの話がいたる所で増えてきた。自分自身の生活をマネジメントすることに必死で、患者のことを考える余裕がないのは充分に理解できる。だが、随分と寂しい話だ。せめて広がる職域やキャリアの話を聞くならば、”理学療法士として”誰のためにどんな仕事をしているのか知りたい。その場で求められる専門性は何なのか。わざわざ芝を自分で青く塗ってまで見せる必要はない。
特別を目指しても、普通を目指しても、どうせ孤独が待っている。ならば増えるモヤモヤをもっと大切にしようと思う。悩みを磨けば個性が光るだろう。この仕事は人間が相手なのだから、みんなで分かり合えるほど容易くない。予測できない流れの中に身を投じたなら、じっと耐え忍ぶ時も必要である。秒針、長針、短針が周回する速さは異なる。
発表を終えると、ありがたいことに参加者から質問をもらった。経験年数は関係ない。臨床について議論を交わす。3年かかってようやく交流が始まった。
『失礼ながら同じことを考えている気がして…』
10期以上離れた後輩が口にした。
全然失礼ではない。私も全く同じこと思ったことがある。恩師に対して「なんでこの人、私の知りたいことを全て知っているんだろう」と何度も思ったことがある。
その瞬間、ようやく何かが繋がって、それがまたこの先も続いていくような気がした。
目には見えない大切なものを確かめられた気がした。

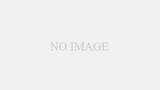
コメント