“趣味は何だっけ”問題は定期的に訪れる。5年に1回くらいの頻度だろうか。
前々回くらいに「”趣味”という概念で考えてはダメ、”何をしているのが好きか”で考えればよし」と自分の中で結論を出した。
そうして解決した事案かと思ったが、また最近ぼんやりと考えている。
原因は至極明快で、加齢(年齢と時代の変化)によるものだ。
時代は繰り返すというが、そのループする周期と自分の人生の波が絶妙に揺らぎ、重なり、離れていく。
話題のそれも、構造レベルでなんとなく知った気になって満足できるし、それを深追いする意義が見当たらない。トレンドを追って見つけた話題を翌日にシェアする場面もない。
YouTubeですら既に平成を懐かしむ懐メロめいた空気が漂っている。アルゴリズムのせいかとおもったが、そのコンテンツには確実に誰か作り手がいる。対面しない同窓会をきっかけにあの頃に想いを馳せる。黙ってただ前を向いて生活しているだけで、時代が回って後ろから追いついてくる。学生と話すと何故か話題が一致する。それ20年前に流行ったやつよ?ってそうだ、こちらは周回遅れなんだわ。
盆が過ぎればなんちゃら。みたいに始まりと終わりが曖昧になって、メリハリも風情もない夏だ。昭和生まれ平成育ちの”ゆとり”の現状を重ねてみたりして。
そろそろ秋に入る頃だろうか。
年相応に興味が移り変わる。よくよく考えると、スポーツやドラマ自体にそんなに興味がない。プレイヤーや俳優といった人間そのものにはとても興味がある。どんなプレーをするのか、どんな表現をするのか。どうしてそれを目指したのか。
誰かの表現を見るのもいいが、やっぱり自分でやりたい派だ。スポーツも芸術も。そうなるとスポーツ観戦ほどつまらないものはない。自分が参加しない競技を見ていると、いてもたってもいられなくなる。なにかやらなくちゃ、と。
誰かに決められたルールの中じゃなくて、誰にも決められないルールの外で働き、輝く人の方が圧倒的に多いと思う。その素晴らしい競技を我々はなんと呼べばいいのだろうか。
人によってはそれが労働かもしれない。仕事が好きなのは、ある意味で不幸中の幸いだ。
生産と消費のバランスが重要だと思っている。買わされている、消費させられていると思ったら負けな気がする。途端に全然楽しめなくなる。誰かの手のひらの上では居心地が悪い。
時間や金銭的コストを気にせず、一心不乱にできる好きなことは何か。しかしそれが中々、難しい。学問でさえ、インプットに偏りすぎるとただの情報消費者になってしまう。知識にかぶれ、頭でっかちになりたいわけじゃない。少しでも足を動かせ。心を燃やせ。
それに比べたらAIの頭は限りなく無限に近いと思える。人間はAIじゃないし、AIは人間じゃない。知性を手放すにはまだ早すぎる。
現象は逆行しない。ヒトとして歩み続ける限り、次の着地に備えないといけない。趣味や好きなことが案外、その足場になると思っている。たとえ未解決のままでも。

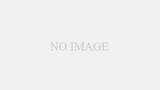
コメント