先日、夏祭り風保護者交流会を無事に終えた。甚平を着た子供達が、かき氷やラムネを堪能したり、ボール投げやゲームに参加して大いに楽しんだ。
娘の保育園で行っている自主的な保護者活動、と言えば伝わるだろうか。保護者役員の経験をきっかけに、そのまま保護者有志に声をかけ、近所にある集会室を借りて、子供達をワイワイ遊ばせる。その時々の遊びを考えたり、お菓子を用意しながら、保護者達は交流を図る。そんな会を定期的に企画している。
年に1〜2回の開催を続けて、今年でかれこれ4年は経つ。
毎回、企画し準備する度に、「なぜ私はこんな面倒なことを言い出したのだろうか」と思う瞬間がある。言葉にするまでもないが保育園児の保護者は仕事で忙しい。自分たちの生活をこなし、仕事をこなし、育児をこなしている。その隙間を見つけて何かしようかと言っても、時間的にも体力的にも負担は少なくない。むしろ少し、精神的な圧迫感さえある。
それでも一定数の保護者が毎回賛同してくれて、準備を手伝ってくれる。子供達のためにと会費を出して、アイデアを出して、時間を作って参加してくれる。
二児の父親として子供達が小さい時にやってあげられることを数えてみると、両手で容易く数えてしまえる気がする。小学生になると、幼児期よりも一歩距離を離して見守ることが多くなる。個人的な感覚だが、小学校生活は”子供達のもの”を指すが、保育園生活は保護者の生活もかなり重複する部分があると思っている。つまり、”親子のもの”という認識がある。母親歴・父親歴のまだ浅い親が、親になるための期間でもある。受動的な態度で保育園にあれこれと期待し、丸投げしていてはビギナー親子が得られるリターンは少ない。
加えてコロナ禍を経験した事が大きい。ちょうど役員をやっていた時がまさに渦中であった。感染拡大を避ける代償として園と保護者、そして保護者同士のコミュニケーションは制限され、登園しても園内には孤独感が漂っていたのは今でも忘れない。誰に頼っても何も解決しない日々だった。
ならば、できることを自分たちでやってみようと、制限する行事やイベントの代わりになればと交流会を始めたのがきっかけだった。その時にできる最大限のことをするのがモットーだ。
保護者、特に母親の孤独感はちゃんと世間的に問題視されている。当時、役員としてあれこれ調べる中で、保護者のための公的サービスが用意されていても、能動的に使うことができないという”使う側の問題”も指摘されていたことを覚えている。
なんとなくわかる気がする。公に向かって、誰か助けてと言うようで、それはどこかで自分を親として足りてないのではないかと認めるような気がする。実際は助けて欲しいくらい余裕がないのに。
保育園生活が始まると生活観が変わり、人生観の見直しを迫られる。そうだろうなと思っていたけど、思っていたより時間がない。自主的に行動を起こすには慣性が大きくなりすぎて邪魔をする。抱える子供の体重以上に何かが重くのしかかる。
お金を払って一時的に肩の荷をアウトソーシングしようが、根本的なものは変わらない。切羽詰まるその手前、さらにその一歩手前くらいの段階で何かできることがあるのではないか。なんて、わざわざ口にするまでもないので、大人しく交流会を企画して、せめて我が子と同じ学年の子どもとその親の顔と名前くらいは知っておこうと思う。困った時はお互い様って言えるように。
風通しの良い育児環境、そして地域社会であれ。
待っていたらあっという間に子供は大きくなってしまう。せめてできることをしてあげたい。というより、自分たちが親であり、地域で見守る大人であることを自覚するためにやれることをやらせて欲しい。
真夏の交流会はいつもギリギリ赤字だったりする。なんやかんやで「アレいいね」「コレいいね」なんて言いながら余計な物を買ってしまったり。それでもリターンの方が大きい。なぜなら与える者が最も与えられることを私は知っているから。
4年も一緒に遊んでいるのだ。大人に向かって挨拶できるようになった自分の子供達の成長や、一緒に遊ぼうと誘ってくれる他人の子供達の成長。そして自分たちの家庭や仕事だけでは得られない充実感。
ひっくるめて、全ては経験したからこそ得られた関係性だ。子供達の卒園まで、その一挙一動をこの眼差しで見守っていきたい。

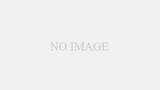
コメント